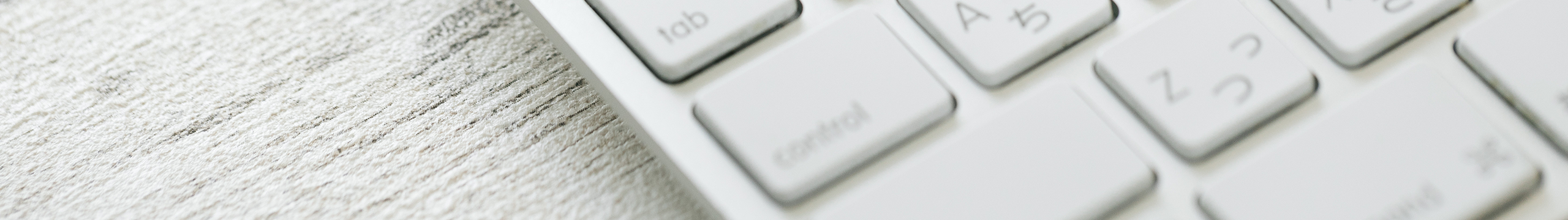2025/06/23
(会報224号=25年5月25日号から転載)
2025年の春闘は23年、24年に引き続き、3年連続で大幅な賃上げとなった。労使は今年を「新たなステージの定着」「賃上げ定着の年」と位置づけ、持続的な賃上げに期待を寄せる。
折しも今年は「春闘70年」の節目にあたる。今春闘の評価を含め過去の歴史を考察し、今後の交渉の戦略・戦術など労使のあり方、さらには賃上げの持続可能性に向けた「春闘の未来」について4人の会員にご寄稿いただいた。(編集部)
春闘の未来にとって必要なこと
浅井 茂利
2025年春闘の課題は、物価上昇を上回るベースアップを、中小企業も含めた日本全体で定着させることであった。
途中経過ではあるが、4月17日公表の連合の集計によれば、
①ベースアップ率の平均は、全体で3・75%、99人以下の組合でも3・39%と、物価上昇を上回る傾向となっているものの、
②集計組合に占める要求提出組合の割合は、昨年同時期77・4%に対し77・7%と、ごくわずかな改善に止まっている
③また月例賃金妥結済組合のうちベースアップ獲得組合は、昨年62・2%に対し62・7%と、これも微増に止まっている
という状況にある。昨年の最終集計では、集計組合の中で明確にベースアップを獲得した組合の割合は41・5%だったが、これがどの程度改善するかは、予断を許さないところである。(ちなみに組合員数で見ると、少なくとも9割程度はベースアップを獲得しているものと見られる)
また、一部経営側からは、いつまでベースアップを続ければいいのだ、といった声がある一方で、昨年を下回った企業では、世間相場並みのベースアップを実施していても従業員から不満が出ている、といったこともあるようだ。こうした状況は、いずれもベースアップの根拠が不明確であることに起因しているものと見られる。
連合では、実質GDP成長率、消費者物価上昇率、日本全体の生産性上昇率のトレンドを念頭に、国際的に見劣りのする賃金水準の改善、労働市場における賃金の動向、物価を上回る可処分所得増の必要性、労働者への分配増などを総合的に勘案して、ベースアップ「3%以上」という「賃金要求指標」を決定しているとのことだが、漠然としているだけでなく、列挙されているさまざまな項目と、要求指標との間に乖離・違和感があり、説得力がないことは否定できない。実際には、多くの主要産別で3%を超える要求基準を掲げ、マクロ経済の動向と乖離・違和感のない春闘を展開したが、連合の要求指標が、物価上昇率さえ上回ればよい、という誤ったアナウンスになる可能性があったことには留意が必要である。
一方、経団連では、2025年の先に描く姿として、「2%程度の適度な物価上昇とともに、1%程度の生産性の改善・向上、これらに対応する賃金水準引上げ(ベースアップ)」という考え方を示している。経団連が明確な、しかも、かつて労働組合側が提唱し、『平成27年版労働経済白書』において「標準的な経済理論が想定する世界と等しいもの」と評価されている「逆生産性基準原理」と同様の考え方を示しているのに対し、連合の反応が「当面の安定した巡航軌道のイメージとも基本的に重なるところが多い」といった程度に止まっているのは、要求根拠の考え方に関する労使共有化の機会をみすみす逃し、今後の春闘に禍根を残す可能性があると考えざるを得ない。 ベースアップの根拠が明確化され、広く共有化されていれば、
①個別企業の支払い能力に関わらず、すべての企業でマクロ経済の動向を踏まえたベースアップを実施すべきであることが明確になる
②年ごとに、ベースアップを行うべきか、どの程度のベースアップが適正か、が明確となり、前年よりも低い、もしくは高いベースアップに対し、労使双方の納得感が得られるということになる。
消費者物価上昇率(総合)は、2023年度、24年度と2年連続で3・0%となっているが、25年度には鈍化が見込まれている。こうしたマクロ経済情勢の変化をきっかけに、ベースアップの根拠の確立を図っていくことが、将来にわたる永続的なベースアップの実施につながっていくのではないか。
経営者主導で「春闘」の形骸化がより明確化
森 一夫
集中回答を受けて3月12日に金属労協が開いた記者会見で「満額回答に至らなかった企業について、その背景や原因をどのように考えますか」と、あるテレビ局の若い記者が質問した。
「近年、満額回答が多いので、満額が当たり前と思うかもしれませんが、過去は決してそんなことはありません。(それ相応の回答ならば)満額回答ではないことが必ずしもデメリットにはならないと理解してください」。こう金子晃浩金属労協議長は答えたが、一昔前なら考えられない珍問答である。
30年低く抑えられてきた賃上げが2023年から急に上昇に転じ、勢いは24年、25年と増している。満額回答や要求以上の回答、さらに回答指定日前の満額での妥結などが、今年も続出した。
連合が4月17日に発表した第4回集計によると、回答の平均賃上げ率は定昇込みで5・37%、中小は4・97%である。賃上げ分(ベア相当)だけの集計では、全体が1万2065円、3・79%、中小が9868円、3・62%に なる。いずれも額、率ともに2015年以降の最終集計と比べて最高である。3月の消費者物価の上昇率3・2%を上回り、実質賃金がプラスになる兆しが見えてきた。
こうした回答状況を、芳野友子連合会長は3月21日の第1回回答集計の記者会見で「新たなステージの定着に向けてよいスタートが切れた」と評価した。
だが労働組合の交渉力の賜物だろうか。1955年に始まった春闘は満70年、長く低調だったが再活性化したといえるのか。内実は、そうとは思えない。
連合は、昨年の賃上げ率が5・1%なのに、今年の要求基準を昨年と同じ「5%以上」に据え置いた。今年も5%台に乗り昨年実績を超えた。「5%以上」の要求に何の意味があったのだろうか。
経営側は総じて23年以降、賃上げに前のめりである。前述の満額回答などは突出したケースだが、高水準の回答を象徴している。
経済がインフレ基調に変わり、人手不足も激しい。国際的に見て賃金水準が低くなりすぎた。このままでは人材を確保できず、従業員のモチベーションも上がらない。今や企業にとって、賃上げは重要な経営課題になったといえる。こうした企業の変化によって、バブル経済崩壊後、進行した春闘の形骸化はより一層はっきりした。ばらばらでは弱い労組が共闘体制を組んで経営側に迫り、高い賃上げ回答を引き出そうというのが春闘の本来の趣旨である。形だけは今も変わらない。マスコミも「春闘」として報じるが、この3年、大勢は経営者主導になり、実際にはすっかり変質した。
この70年の間に環境が様変わりしたためである。まず製造業を含めて経済のサービス化が進んだ。ホワイトカラーの比重が増すとともに、有期雇用が増えて、雇用が多様化した。賃金も年功賃金から成果給、ジョブ型へと、個人別に決める方向に変わってきた。
このため大手製造業が相場をつくれば、業種や規模を超えて波及するわけではなくなった。個人も妥結結果よりも自分の成果が気になり、労組の求心力は低下した。
記者会見で芳野連合会長に「『春闘』という看板を変えてはどうか」と尋ねてみた。答は「時代の流れで『闘争』という言葉が合わなくなっているとの声が職場から上がっているのは事実ですけれど、連合の中で引き続き検討していきたいと思います」だった。
「春闘」の看板に固執せず、取り組み方を抜本的に改めないと、賃金決定への労組の関与は強まらない。労組の推定組織率も組員数も下降線のままである。トランプ関税で景気悪化が予想される。賃金が上がらない時代に逆戻りする危険はまだ消えていない。
「構造変化」の25春闘結果と課題 分配の歪み是正へ「力」と政策強化を
鹿田勝一
政財界が賃金抑制反省しベア
春闘70年、連合結成35みらい年目の2025春闘はこれまでとは異なる構図で闘われた。昨年の総選挙の敗北や物価高、人手不足から政財界とも「物価を上回る賃上げ」を言わざるを得なくなり、政策課題でも国民要求を部分的にも受け入れざるを得なくなっていた。
とりわけ経団連は50年目の経労委報告で「ベアは論外」(12年)など四半世紀にわたる賃金抑制について、「国際的な賃金水準の低迷をもたらした」と反省。今後の賃上げは「物価上昇(実質賃金維持)と生産性向上(GDP)に対応する賃金水準引き上げ(ベア)」を「社会性の視座」として提起した。労働分配率の低下も指摘し、内部留保の賃金活用も初めて明記した。
石破政権も16年ぶりの連合との政労会議で「中小企業支援政策の総動員」を表明している。
連合の相場形成波及と分散
連合は「経済社会のステージ転換」を掲げ、「昨年以上の相場形成波及」をめざした。回答水準(4月17日)は1万7015円(5・37%)で、33年ぶりの高水準とされた昨年並みを確保し、芳野友子会長は「賃上げノルム(規範)ができ、定着へ」と評価している。
課題は回答のばらつき。「製造業」「商業流通」などは昨年比でマイナス幅が大きく、プラスは「交通運輸」「サービス・ホテル」の2業種のみで、「追い風」春闘でも昨年比0・17ポイントの微増だ。連合が掲げた「分配構造の歪み転換」からも不十分な水準とされている。
要求水準も課題。連合のベア3%以上(定昇込み5%以上)は物価ミニマムであり、満額獲得しても、生活向上も分配の歪み是正もできない。産別の多くが連合より高いベア4~5%を掲げた。
格差是正へ大手・中小健闘
25春闘で大きな課題となった格差是正は運動成果をあげている。
連合も89年の結成後、90~95年までは中小が大手より高率妥結をしていた。格差が拡大したのは02年~04年の春闘からである。経団連は「春闘終焉」(03年)など賃上げ抑制を強めた。連合も「ベアゼロ・定昇中心」へと要求を自制した。
曲折を経ながら、連合は25春闘で中小支援へ11年ぶりに格差是正として、5%要求に1%を上積みして1万8千円以上、6%以上の要求を設定。中小は30年ぶりの6・57%要求となった。回答水準は大手より低いが、昨年より上げ幅で大手を上回り健闘している。
運動では各産別が相場形成と波及の春闘メカニズムを強化。「親組合などが中小支援へ経営要請強化」(基幹労連)、「産別・地方の役員が単組に出席交渉」(JAM)、「単組の妥決権を産別会長が掌握し、中小労組の共闘強化」(UAゼンセン)、「産別単組の85%へ大手水準波及」(電機連合)などを展開した。
分配構造転換へ「力」と政策
今後の課題は、賃上げの「定着」と水準である。「社会性の視座」(経団連)は実質賃金確保とGDPであり、毎年ベアは約5%(定昇込み7%)がミニマムとなる。さらに格差是正や人材確保、生計費、国際水準への到達もプラス要素となる。獲得には連合方針の「スト権」確立と行使も課題となろう。
格差是正では大企業の平均賃金37・7万円に対し、中小30・4万円の是正へ個別賃金の改善が課題となる。雇用形態やジェンダー平等では同一労働同一賃金や最賃引き上げ、組織拡大も重要となる。 分配構造の転換では「力」とあわせ、政策要求の実現も重要課題だ。石破首相は「賃上げへ政策総動員」を表明。経団連も政府施策で「業務改善助成金」など15項目を例示。連合は労務費の価格転嫁を重視し、全労連は内部留保の還元などを提起している。
今後、政策闘争は、トランプ関税による輸出減・雇用・賃金縮減などに対する戦線課題となる。
「何並み」賃金を目指すのか―春闘の再構築に向けて
荻野 登
草創期の春闘が目指したのは「ヨーロッパ並み」賃金だった。高度成長期・政府の所得倍増計画の追い風を受け、70年代にはその目標を達成した。
転換点は石油危機で、大幅賃上げ路線から転換。経済整合性論によって過年度物価プラスアルファという自制的な要求方式が定着する。それからは時短や制度・政策要求もからめて、「欧米並みの生活大国」を目指した。
しかし、平成不況によって生じたデフレ経済下で賃上げが止まり、賃金水準は20年にわたって停滞した。さらに雇用の二極化で格差問題も顕在化、長時間労働は是正されず、「生活大国」は実現できなかった。
この間、賃金が上がっているときも停滞しているときも春闘は続いた。そしてその機能と役割は相場形成とその波及メカニズムだった。それが70年たった今、その役割を果たしているのだろうか。
いま問われているのは「何並み」を目指しているのかを明確にすることではないだろうか。ところがいまそれか困難なのは、全体としてめざすべき「何並み」が見当たらないことだろう。
2020年春闘のあたりから経営側は国際比較でみた日本の賃金水準が先進国の後塵を拝していることに危機感を募らせた。「先進国並み」の賃金を払えないと人材が確保できないことが、ここ数年の初任給バブルといえる状況につながっている。
では、労働側は「先進国並み」を求めればいいのだろうか。高度成長期と異なるのは、新たな二重構造問題ともいえる雇用形態間の賃金格差への対応を織り込まなければならないことだろう。
石破政権が打ち出している最低賃金1500円は、「先進国並み」水準かもしれないが、労使は政府主導の動向をけん制している。かりに1500円になると月給に換算すると25万円程度になり、労組が雇用形態各格差の是正に向けて目指す「正社員並み」が実現してしまう。しかし、こうした国家統制的な賃金政策で物事が進んで行っていいものだろうか。
過去3年の高水準の賃上げは、物価高と人手不足が促している面が大きいものの、厚生労働省の調査によると、「世間相場」を賃金決定の要素として重視する企業が増えている。
労働組合の要求を見てもやはり世間並み水準を重視したいという思いは強い。個別賃金の要求をみると、自前のデータではなく、賃金センサスのデータを使っているものが多い。
しかし、ここ数年の初任給の急激な伸びによる賃金体系の変化は、賃金カーブの中だるみにつながり、早晩これまで使ってきた公的データでは対応できなくなるだろう。
賃金水準の世間相場を把握するためには、改めて、政府統計だけではなく、労働組合自らの調査による実態把握が欠かせなくなる。経営側にしても、労組の主張に向き合う場合、独自のデータ把握が必要になるだろう。いずれ にしても実態把握のための調査がこれからの賃金政策立案の基礎となる。
マクロで目指すべき最低賃金の水準は、「先進国並み」で政労使の思惑に大きな差はないかもしれない。では、産業・企業レベルとなると、話はやや複雑になる。
「何並み」を目指すにしろ、まず、全体像を把握しない限り、目指すべきターゲットもぼやけてしまう。男女間賃金格差の是正に向けて、情報公開を求める政策が導入されているが、放っておくと、比較できる賃金水準の公開 を求める政策が打ち出される可能性も排除できない。
労使自治による賃金決定という大原則は死守しなければならない。そのためにも、労使による主体的な情報収集と公開によって、世間相場の形成と波及メカニズムを生む春闘の再構築に期待したい。