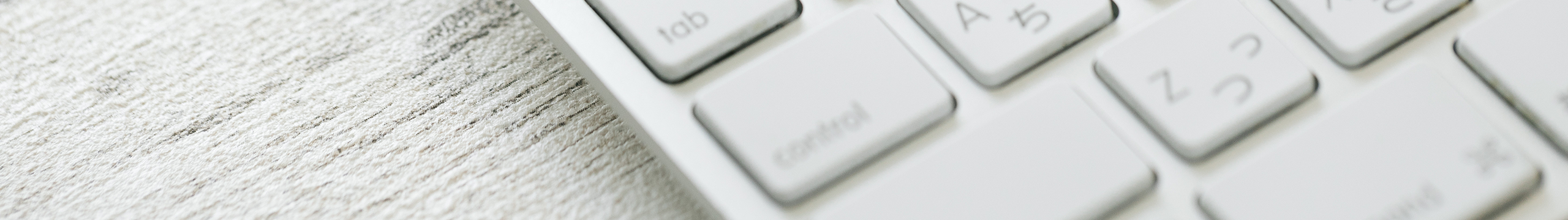2024/10/28
(会報221号=24年10月5日号から転載)
2024春闘の賃上げ率は連合集計で5.10%、また、経団連の主要企業の賃上げ率も5.58%と、いずれも33年ぶりの高水準となった。また、中小企業は連合が4.45%(300人未満)、経団連が4.01%(500人未満)。こちらも近年にない大幅な賃上げ率となった。しかし大企業と中小企業の格差は依然として大きく、価格転嫁も道半ばだ。今春闘の結果をどう評価しているのか、さらに来春闘の戦略をどう描いているのか。連合の仁平総合政策推進局長と経団連の新田労働政策本部長に聞いた。
 連合会館
連合会館 経団連会館
経団連会館ステージ転換に向けた大きな一歩
連合 総合政策推進局長 仁平 章氏
――連合の最終集計は、「定昇相当込み賃上げ計」の平均賃上げ率は5.10%と、33年ぶりに5%を超える高い水準となった。どう評価しているか。
300人未満の中小組合が4.45%、賃上げ分が明確に分かる組合のいわゆるベア分は3.56%、中小は3.16%。2023年度の消費者物価(総合)3.0%をいずれも上回っている。今年の春闘のスローガンには「みんなで賃上げ。ステージを変えよう!」を掲げた。「わが国経済社会のステージ転換をはかる正念場」との時代認識を労使で共有し、物価高による家計への影響、人手不足による現場の負担増などを踏まえ、中長期的視点を持って粘り強く交渉し、主体的に大きな流れを作った結果だと考えている。まさにステージ転換に向けた大きな一歩として受け止めている。
2023年は四半世紀続いた2%台の賃上げが動いたという意味では一つの転換点だと思うが、生活向上分までは届かなかった。5%台は「ステージ転換に向けた大きな一歩」と評価しているが、ステージの転換が今年完成したということではなく、生活向上の流れをしっかりと社会に定着させていくことが課題だ。大きな一歩の背景には物価高や人手不足などの経済的要因もあるが、運動面において連合方針をしっかりと受け止めた厚生組織、単組が要求し、交渉してくれた結果だと思っている。
――集中回答日は「満額」ないし「要求以上」の回答が相次いだ。メディアの中には、もっと要求水準を高くすればよかったのではないかという意見もある。
我々は運動家だ。2023年の10月、11月の段階でどうすれば運動を組み立てられるのかを重視し、取り組んできたし、それに見合った結果も出ている。メディアの方々は回答の局面に焦点を当てるが、どれだけ本気で取り組むことができたかを重視すべきだと思う。23年の連合方針は定昇込み「5%程度」に対し、実際に要求した組合の賃上げ率の平均は4.5%程度だったが、前年よりはしっかりした要求をしている。今年は「5%以上」に対し、要求の平均値は5.85%だ。連合の闘争方針を受けて、前年より賃上げ目標を引き上げた構成組織も多く、幅広い産業で積極的な賃上げ要求作りを行い、しっかりと交渉したことが結果に結びついた。「満額回答」に注目するより、要求や交渉のプロセスに注目してほしい。それなくして結果はありえないと考えている。
――中小の組合は4.45%だが、1000人以上の企業の5.24%とは依然開きがある。格差是正への取り組みについてはどう評価しているか。
中小組合は昨年に比べてがんばったと言える。全体的に健闘しているが、平均を下回っていることもよく認識しておくべきだろう。また、賃上げの結果だけではなく、なぜそうなったのかもよく考える必要がある。我々の受け止めとしては、一番大きな原因の一つは、価格転嫁が中小企業では十分に進まなかった、あるいはこれまでの取引慣行の中で、価格の改定ができていないところに問題があったのではないかと思っている。産別の話を聞くと、中小がおしなべて取れなかったわけではなく、価格転嫁や取引価格の改定ができたところは大手並みに獲得できている。獲得できなかった組合は概ね価格転嫁がうまくできなかったところが多いという話も聞いている。したがって大手並みの5%台を目指していくとすれば、価格転嫁をどのようにして実効性のあるものにしていくかが今後の課題だと考えている。
――来春闘の持続的な賃上げに向けてどう行動していくのか。
昨年も今年もそうだが、マスコミの皆さんは物価との関係ばかりに注目しているような気がする。私の問題意識としては、物価上昇分だけ取れればよいということではなく、物価を上回る生活向上分を取ることもセットで考えていきたいと思っている。マクロ政策として物価を安定させる中で、マクロの生産性向上は1%ぐらいあると思っているし、中期的にはもっと引き上げていく必要がある。足下の生産性向上が1%弱であれば、それに見合った1%の生活向上分をしっかりと勝ち取っていく。経済が良くなるのであれば、働く人の生活もそれに見合って良くなるのは当たり前のことだ。その当たり前ができなかったこの30年こそが問題であり、そのための転換点を今回作ろうとしている。そのことをしっかりと主張していきたいと思っている。
――連合の「まとめ」(7月19日)では、今年の賃上げ配分について「人材確保のために初任給を大幅に引き上げる一方、中高年層への配分を相対的に抑制するなどの傾向もあるものと推測される」と書いている。賃金原資の配分も問題だという認識か。
単組の交渉の中で賃上げをどう配分するかは、それぞれの状況があり、連合として配分について踏み込んだことはほとんどない。しかし今年はあえて言及した。初任給の回答集計では高卒・大卒の賃上げ率はともに約6%と、1991年以来の伸びを示している。全体が定昇込み5%に対し、初任給6%ということは若年層に多く積んで中高年層は相対的に薄くなっていることが想像される。もちろん初任給の引き上げについては5%の配分の外側でやっている労使もあれば、全体の配分の中で考えている労使もあるだろうと思う。今後実施する労働条件調査で改めて点検したいと思うが、中高年層への配分を抑制する傾向があることが推測される。
問題意識としては、5%取れたからよいというのではなく、どのように働く人の暮らしの向上に繋がっているのかが最も重要だ。労働組合として賃上げ原資の配分にもしっかりと関与する必要がある。一人ひとりの暮らしや職場のがんばりなどにどのように反映させるのかについて労使交渉でよく考えてほしいとの注意喚起で提起した。これまで定昇や賃金カーブ維持分の獲得が交渉の中心になり、カーブのどこを重視し、配分していくのかという議論が少し低調になってきた中で、改めて原則に立ち返り、賃上げ交渉に臨んでほしいと思っている。
賃上げ「加速の年」から「定着の年」に
経団連 労働政策本部長 新田 秀司氏
――経団連の大手企業の妥結結果は定昇込み賃上げ率は平均5.58%、中小企業は4.01%となった。この結果をどう評価しているか。
大手の5.58%は1991年以来、33年ぶりの高水準となり、金額の1万9210円も比較可能な1976年以降、過去最高額になった。中小企業もアップ率4.01%、引上げ額1万712円でいずれも92年以来の高い水準となった。我々は、ベア実施企業が増えてきた2014年から賃金引上げのモメンタム(勢い)が始まって潮目が変わったと見ており、その後、コロナ禍の21年を除き、この流れは継続している。こうした中、23年のアップ率は3.99%(大手)を記録し、「転換・起点の年」になったと考えている。今年は賃金引上げのモメンタムの維持・強化を呼びかけて取り組んできた結果、先ほどご紹介したように近年にない高い水準の引上げとなり、今年は「加速の年」になったと位置づけている。
さらに言えば、この賃金引上げのモメンタムを来年も維持・強化し、「定着の年」にすることが重要と考えている。高い水準での賃金引上げが3年間続けば、傾向として根付いた、定着したといえるのではないか。23年の「転換・起点の年」から「加速の年」、そして来年は「定着の年」にしていく。加えて、賃金は上がっていくものという認識を社会的規範として定着させていければと思っている。
――賃上げに関する経営者の意識も変化しているのか。
毎年、「経労委報告」公表後にその説明で地方を回っている中、昨年から変わったと感じるのは、ベアを含めた賃金引上げに前向きな経営者が多くなっている点だ。物価の上昇による社員の生活への影響を考えてという理由もあるが、人材の確保の観点から賃金引上げが必要という発言が多く聞かれた。今年はそれに加えて、人材の「定着」を理由に挙げる方が増えたように思う。収益が伸び悩む中で賃金を引き上げることは経営者にとって大変なことには違いないが、必要な人材が確保できず、優秀な社員が退職してしまっては事業継続そのものが危うくなる。賃上げをネガティブに捉えるのではなく、企業経営に必要な「人への投資」として前向きに検討・実施していくことが社会的にも求められている。そのような方向で、賃金引上げの機運が醸成されてきていると感じている。
――大企業の賃上げ率5.58%に対し、中小企業は4.01%と依然開きがある。大企業や取引先への価格転嫁が重要な鍵を握ると思うが、どういう取り組みをしているのか。
わが国全体での賃金引上げの機運醸成には、企業のほとんどを占める地方の中小企業が「構造的な賃金引上げ」を実現できるかにかかっている。同様の言い方に「持続的」な賃上げという表現があるが、我々は「構造的な」賃金引上げと言っている。単に賃金引上げを続けていくのではなく、賃金原資を継続的に確保し、構造的に賃金を引き上げていくという意味でこう表現している。そのために、まずは政府の支援策も活用しながら中小企業自身が生産性の改善・向上に主体的に取り組み、そうした中小企業をサプライチェーン全体でサポートする必要がある。適正な価格転嫁は当然との認識を発注者側、受注者側で共有し、原材料費やエネルギー価格だけではなく、運送費や労務費・人件費の増加分も含め価格転嫁することが望まれる。大企業は中小企業からの申し出をスムーズに受け入れられるよう、経営層から取引担当者に至るまで社内での周知徹底を図る必要がある。
――適正な取引慣行の実行を経営者自ら宣言する「パートナーシップ構築宣言」をしている経団連会員企業は昨年12月末現在、51.7%だ。進捗状況はどうか。
今年4月時点で56.7%と承知している。その後、経団連は5月に、パートナーシップ構築宣言の趣旨を徹底するために「企業行動憲章」の第2条を改定し、「パートナーシップ構築宣言に基づき、サプライチェーン全体の共存共栄を図る」と明記した。これは経団連の全会員企業が順守するものであり、我々としてはかなりの決意をもって取り組んでいる。今後も呼びかけを強化していきたい。
昨年、経労委報告の説明で地方を回った際、複数の経営者からなかなか価格転嫁の話ができないという話を聞いた。今年は、労務費についてはまだ進まない部分があるが、原材料費やエネルギー価格の転嫁に関する交渉はしやすくなったという声が明らかに増えてきたと感じている。
――中小企業の構造的賃上げにおいては最低賃金も重要な要素だと思う。最賃の役割をどう考えているか。
中小企業の賃金決定において、法定の地域別最賃の水準も当然考慮しなければならない要素の一つだ。近年の最賃の大幅な引上げが、企業の経営、とくに地方の中小企業の経営に及ぼす影響は以前より大きくなっている。そういう意味でも、構造的な賃金引上げを実現し、最賃の引上げにも対応していく必要がある。あわせて、民間企業が決定する自社の賃金と違い、最賃は最低賃金法を根拠として、企業の業績状況に関わらず、すべての企業に罰則つきで強制適用されることからすれば、中小企業自身が取り組むことももちろん大事だが、政府が実効性ある支援策を講じていくことが不可欠だ。
――来年の構造的な賃金の引上げについて政府そして労使の果たすべき役割とは何か。
構造的な賃金引上げの前提として、政府・日銀がこれまでの共同声明に基づいて2%程度の物価水準を安定的に実現していただきたい。その上で、物価動向も重要な考慮要素として掲げながら、賃金引上げを積極的に考えていくことが望まれる。2%程度の適度な物価上昇のもとで、それに見合った賃金引上げについて、ベースアップを有力な選択肢として検討していく、あるいは諸手当や賞与・一時金など様々な選択肢の中から自社に適した賃金引上げ方法を考えていくことが求められている。
物価が緩やかに上昇し、それに見合った形で賃金も上がっていく。そうした「構造的な賃金引上げ」の実現に向けて、来年も賃金引上げのモメンタムを維持・強化し、賃金引上げをしっかりと「定着」させ、それを構造的に継続していくことが大事だ。各企業労使がしっかり話し合い、自社にとって適切な賃金引上げの水準と方法を見出していただくよう、引き続き呼びかけていきたい。