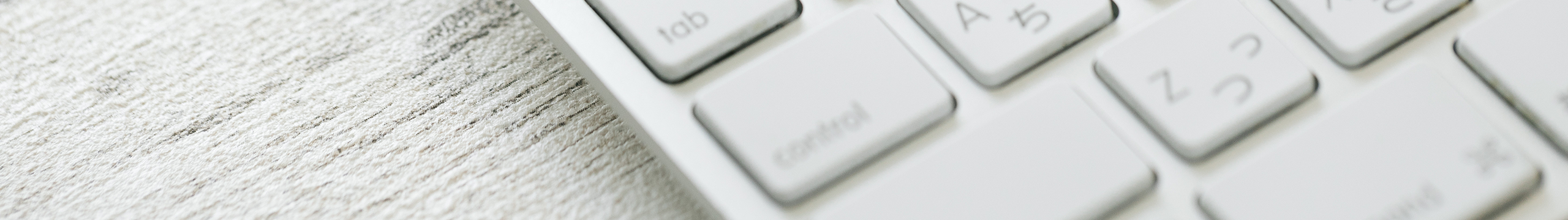2023/06/12
物価高を背景に30年ぶりの高水準の賃上げとなった23春闘。春闘前から賃上げを表明する企業も続出し、政・労・使が足並みを揃えるなど異例の展開となった。今回の賃上げは環境変化による一過性のものにすぎないのか、あるいは持続的賃上げに向けた始まりなのか。今春闘の評価と継続的な賃上げに向けた今後の課題について、4人の会員にご寄稿いただいた。(編集部)

経営側リードの今年の賃上げ 低賃金化で労使は共犯
会員・森 一夫
連合が4月11日に集計した今春の賃上げ交渉の結果は、定昇込みで1万1022円、3・69%である。前年同時期と比べ、それぞれ約1・7倍に跳ね上がった。
「想像以上に手応えを感じている。今年は出発点であって、(賃上げは)何年もしつこくやっていかなければならない」。4月25日付の日本経済新聞に載ったコメントである。連合の芳野友子会長かと勘違いしそうだが、経団連の十倉雅和会長の言葉である。
これが象徴するように、今年は経営側リードの賃上げ交渉だった。とはいえ経営側は、30年も実質賃金がほとんど上がらない状態にした責任を免れない。労使自治だから、労働組合の責任も大きい。日本を低賃金国に転落させた点で、労使はいわば共同正犯である。
さすがに経営側はこのままでは、国内外で人材獲得競争に劣後するので、まずいと悟ったのだろう。
経団連の経営労働政策特別委員会報告は、賃金水準の相対的低下により、「グローバルレベルでの人材獲得において、わが国の競争力は低下している」と警鐘を鳴らした。実際に、4月13日付日経産業新聞によれば、中国の自動車産業と賃金水準が逆転して、日本から人材が流出しているという。
このため今年は、満額回答が自動車などで続出したほか、要求を上回るベースアップの回答も出るなど、異例の展開になった。さらに初任給引き上げやパート従業員への積極的な賃上げも広がった。
低すぎる賃上げ要求
一方の労組側は感度がまだ鈍い。連合は、今年の賃上げ要求基準をベア3%プラス定昇2%で「5%程度」と決めた。賃上げムードが例年になく高まっているのに控え目だ。連合のある幹部は「あまり高くすると闘えないという組合があるので」と内情を語っている。
2016年以来、連合が要求基準を4%程度にとどめてきたのも問題である。企業が好決算の年でも変えず、賃金抑制の片棒を担いだといえる。今年目立つ満額回答も喜べまい。要求が低すぎたとも考えられるからだ。物価上昇を勘案すると、マクロ的に定昇込み4%未満の賃上げでは、ベアは2%前後で、実質賃金の低下は避け難い。
4月17日の連合総研のシンポジウムで、藤村博之労働政策研究・研修機構理事長が、今の労使関係について「労働組合が遠慮しすぎるのが気になる。経営側と同じ考え方をしているのではないか」と指摘した。来春に向けて重要な課題は、労組側が、企業別組合の限界を超えて、労組本来の役割をしっかり果たすことである。
「ポスト春闘」に向けて 賃上げ機運醸成役は労働組合
会員・荻野 登
2023春闘は異例づくめの展開となり、いまのところ30年ぶりの高水準(大手は3%代後半)の賃上げが確実な情勢となっている。
恒例の民間エコノミストなどの予測を1ポイントほど上回っている。なぜ予測が外れたのか。データには表れない「賃上げ機運」を把握できていなかったのかもしれない。
今季、その機運を醸成したのは、経営側だろう。昨年後半から大手企業のトップから賃上げに積極的な発言が相次いだ。その声は年明け早々の新年祝賀会でピークとなり、今までにない空気感が形成される。岸田首相もこれに呼応し、「インフレに負けない賃上げ」を要請した。
2月上旬に金属大手の組合が要求提出直後から、さらに異例の展開となる。22日にトヨタ、ホンダが満額回答で、事実上の決着となり、3月に入るとイオングループの各企業から正社員5%、パート7%を軸とする高い水準の回答が続出。さらにIHIがほぼ半世紀ぶりとなる満額回答で決着するなど、「満額・早期解決」が、今季の異例さを端的に示す動となった。
そして、3月15日の集中回答日に金属労協傘下の8割超の組合が満額で決着。早期・満額解決した企業が事実上のパターンセッターとなり、その水準は同一産業内に波及した(総合重工、食品等)。パート時給の引き上げ相場については、イオンの影響は絶大だった。
労使トップはコメントで、今後の課題を中小への波及と賃上げの継続性をあげた。政府も価格転嫁の取り組みや非正規雇用の底上げに向け政策を総動員するとし、中央メーデーに出席した岸田首相は「賃上げの先頭に立つ」と力を込めた。
経営側が賃上げ機運を醸成
今季交渉において、賃上げの機運を醸成したのは経営側といえるが、「機運」だけで大方の予想を上回る賃上げに結び付いたのだろうか。
物価高騰、人手不足に加え、ポストコロナで経済が再起動する中、人材の確保・定着は重要な経営課題となっている。さらに先進国の中で見劣りする賃金水準も高水準の賃上げを後押ししたといえるだろう。
想定を超える賃上げを促した要因は複合的だが、差し当たって労働組合はその要因分析を十分行う必要があるだろう。物価が落ち着いて賃上げがストップしてしまっては、元の木阿弥となってしまう。
特定産業の賃上げが産業を超えて波及する「トリクルダウン型」春闘は行き詰まりを見せている。ここから脱却した「ポスト春闘」に向けて、来季の賃上げ機運醸成役は当然ながら政府ではなく、労働組合が担う番ではないだろうか。
連合のステージ、これからが本番
会員・横舘 久宣
過去10年、2%前後で推移してきた賃上げが本年春闘でいきなり3%台後半に跳ね上がり、春闘の賃上げメカニズムが再稼働したかとの見方も出た。連合の芳野会長は会見で、高い水準の回答が出ていることについて「加盟組合の執行部が自社の状況、人手不足も含め、様々な点で会社との交渉により引き出した結果ではないか」と語った。
それはその通りかもしれない。だが今季の様変わりを見ると、物価高騰が広がり、人手不足が深刻になりつつあるなか、賃上げをしなければ物は売れないし、求人にも事欠くことかもしれないと、回答する側が自分ごとに沿って気前良くなったからではないか、と勘繰りたくもなる。
労組は緊張感が不足している
労働側が使用者側と交渉の場で厳しく対峙してきた様子が近年感じられなかったからだ。
ずいぶん前になるが、大手水産会社の元社長から聞いた感想が思い出される。「昨今、労働組合の経営に対する理解と認識が深まり、組合の経営に対する物分かりが良くなり過ぎて、いわゆる緊張感がやや不足気味ではなかろうか」。普段は労使というほのぼのとした人間関係でもときにはピーンと張りつめた緊張関係が必要ではないかと述懐していた。
今春闘の結果を踏まえ、2024春闘では組合は一層の待遇改善を求め会社側と緊張感をもって対峙することが期待されるが、ナショナルセンターの連合のステージはこれからが本番だ。課題は多い。
例えば、芳野会長が会見で強調した23春季生活闘争方針の一つが、「適切な価格転嫁によるサプライチェーン全体でのコスト負担」だ。「労務費を含めた価格転嫁をこの時期だけでなく年間を通じて改善していけるよう発信していく」と言う。そのほか税制改正への取り組み、年金、医療・介護、子育て支援など社会保障制度の充実など重い課題が並ぶ。これら課題に関し、使用者団体や政府および関係機関と厳しく対峙し、社会一般を味方につけ影響力を発揮することが望まれる。四季咲きのバラではないが、節目ごとにタイミングを計って広く社会にアピールする存在でありたい。
考えてみれば、連合はまっとうな大きな社会関係資本(ソーシャルキャピタル)の一つである。その特性を発揮して、産業や経済といった枠から踏み出し、国政全体に対してもしっかり関与することが期待される。たとえばの話、外交問題の根っこの韓国元徴用工訴訟。われ関せずを決め込む産業界に対し、韓国側が望む〝誠意ある呼応〟に何らかの関わりを持つよう呼びかけることもありではないか。
「根拠のある賃上げ」に向けて
会員・浅井茂利
4月25日の連合「回答速報」掲載の293組合について独自に分類したところ、満額回答32.8%、満額を超える回答8.5%、9千円もしくは3%以上の回答21.5%となっている。物価上昇をカバーする回答が2割強とは言え、4割以上で満額もしくはそれを超えるという異例の展開となった。
今春闘の特徴は、労使対立というよりも、大転換を強く意識し対応した労使と、デフレマインドから抜け出せていない発想とのせめぎあいであったと言える。
経団連の経労委報告では、「長く続いたデフレと低成長にピリオドを打つ絶好のチャンス」として、「社会性の視座」に立ち、「企業の社会的な責務」として、「物価動向を重視した賃金引上げ」を企業に求めた。十倉会長も記者会見で、連合方針に理解を示し、ベアによる物価への対応を強調、満額回答の動きの拡大に期待を表明した。
一方、労働組合では、物価上昇を賃上げ根拠とすることに躊躇も見られた。物価が下落した場合の「賃下げ」に対する懸念からということであれば、まさにデフレマインドということになるだろう。
支払能力重視から賃金の社会性重視に転換を
日本以外の主要先進国と韓国の計7か国で最近50年間の物価上昇率を見ると、マイナスになったのは350年間中の4年間にすぎず、オーソドックスな金融政策が実施されていれば、物価の下落がほぼないのは明らかである。植田日銀も、デフレを容認しないオーソドックスな金融政策を踏襲していくものと見られ、コストプッシュインフレが収束しても、物価は継続的に上昇していく前提で春闘に臨んでいく必要がある。具体的には、
- 経労委報告では、「実質的に、しかも経済成長に見合った」賃上げをめざす「経済整合性論」を高く評価している。マクロの実質生産性の向上と物価上昇とをベースアップの目安とする「根拠のある賃上げ」を実現する。
- 支払能力重視から賃金の社会性重視に、労使の意識転換を図る。製造業の売上高人件費比率は、欧州諸国が15~20%なのに対し、日本は11%程度に止まっており、「企業には支払い能力がない」という思い込みを払拭する。
ことが不可欠である。
賃上げは若年層に目が向きがちであるが、日本経済に相応しい賃金水準を取り戻すためには、継続的な賃上げに加え、90年代後半以降、低下してきた中高年の賃金水準の回復を図り、正社員とそのほかの従業員との同一価値労働同一賃金を確立していく必要がある。