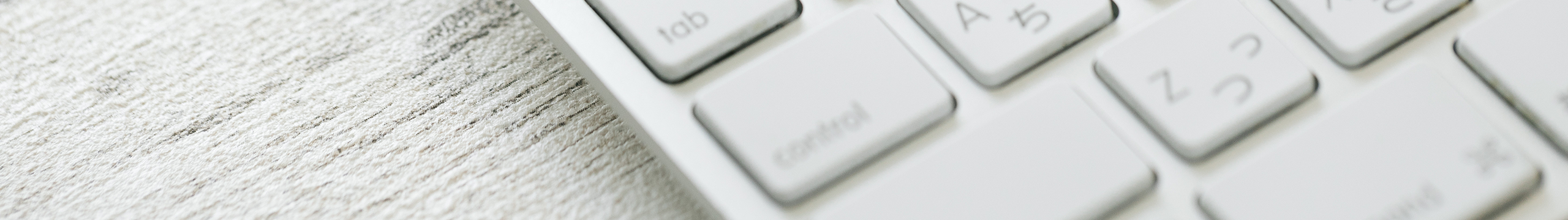2024/12/02
幹事・勝田智明
1958年生まれの私にとって、子どもの頃、戦争と言えば、ベトナム戦争であった。育った横浜の港からは、修理された戦車が積み出されるということで、反対運動があり、知り合いとなった空軍基地である調布の関東村在住の米国人は、尾崎紀世彦を流しながら、自分もベトナムに派遣されるかもしれないと話していた。
ベトナム戦争もパリ協定で終わるかと思えば、その後の北ベトナムによる南北統一、カンボジアでの虐殺、ベトナムによるカンボジア侵攻と続き、世界は、ボートピープルを含む大量のインドシナ難民を見ることになった。
ベトナム戦争に対しては、日本の労働組合は反戦平和に向けた運動を展開し、戦争反対に向けて国内の世論を喚起すると共に、戦車の輸送を妨げることで米軍の活動を遅らせる等の成果を得ていたが、平和の構築という点では、大きな結果につながったとは当時の私には思えなかった。
そもそも、労働者側、使用者側を問わず、労働問題に関わる者は、ILO設立の目的である社会正義を通じた平和の構築については、世界の労働関係者もILOの活動に参加することで一定の貢献をしているが、それ以外にどのようなことができるであろうか。
1995年に私が英国に赴任した頃、未だに北アイルランド紛争が激しく、日系デパートでも爆破予告があったとして、突然、客も全員外に出されるといったことも起こっていた。当時、ロンドン駐在の各国労働アタッシェは度々集まり、労使の指導者を招いて、話を聞いたりしていたが、その中で、ILOロンドン事務所長を招いた会合があった。ロンドン事務所は、英国のみならず。アイルランドも管轄しており、管内の産業別労働組合には、英国本土、北アイルランド、アイルランド共和国のすべてを組織する組合や北アイルランドとアイルランド共和国を組織する組合もあり、労働組合間の対話により、相互間の理解と信頼醸成に努めることにより、北アイルランド紛争の解決に向けた取組を行っているとの説明があった。その時点での率直な感想としては、このような取組にどれ程の効果があるのか疑問に思っていた。
1996年の英国のナショナルセンターであるTUC(労働組合会議)の大会を傍聴していた際、偶々、イスラエル労働党関係者と話す機会があった。その際、日本の行っている労働関係者招聘事業で、イスラエル、パレスティナの両方の代表を一緒に招いて頂き、公式プログラムのみならず、食事、移動等を共に過ごすことにより、帰国後も両者間の対話に大きな成果を上げており、日本の取組に敬意を表すると共に感謝したい旨言われた。初めて、労働関係者の取組は、戦争を直ちに防止できないとしても、平和の構築に向けて貢献することができると実感することができた。
この事業は、当時、途上国の健全な労使関係育成を目的として、当時の労働省から労使に補助金を出して行っていたもので、労働組合関係者の招聘については。国際労働財団(JILAF)が実施していた。制度的な政府の補助事業は廃止されたが、現在でも、JILAFによる自主事業としての労働組合関係者の招聘は、行われている。
このような取組が激しい戦闘を行っている時点では実現可能とも、効果があるとも思えないが、ある程度落ち着いた時点であれば、効果を期待できるのではないかと考えられる。今後とも、労働関係者の取組で。クロスボーダーの関係者間の信頼関係が平和の構築に役立つことを期待したい。