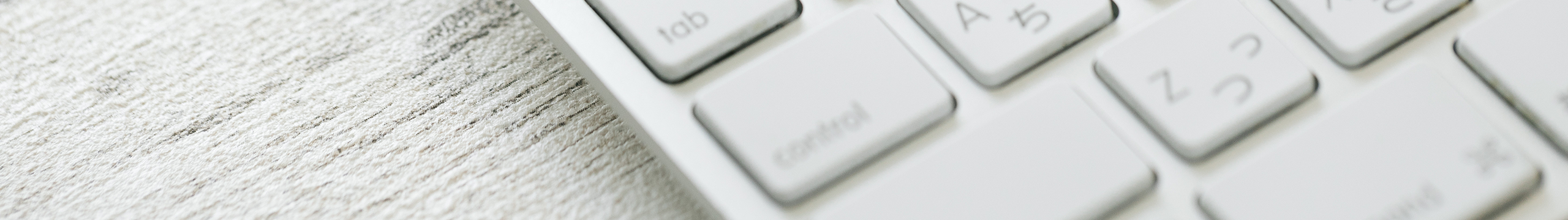2024/12/09
代表代理 君嶋 護男
戦争について考えるとき、思い出すのは、高校、大学の頃、しばしば自宅で行っていた父との「論争」です。父は元職業軍人で、しかもかなり上位の階級にあり、戦後は会社を経営したものの、うまくいかなかったことから、恐らく「昔は良かった」との思いで戦前を美化した考え方を持っていたものと思われます。私と4年上の兄は、そうした父の態度、考え方がたまらなく嫌で、しばしば議論を闘わせたものでした。私と兄は、決して仲の良い兄弟ではなかったのですが、この時だけは共に父と闘ったものです。
我が国では、先の大戦以降、約80年にわたって戦争が行われていませんが、目を世界に向けると、ウクライナや中東で激しい戦いが展開され、多くの人命が失われるという悲惨な現実が連日のように報道されています。私自身、こうした報道に接する度に、胸を痛め、早く平和が訪れて欲しいと願いながら、その解決のために特段の行動を起こしていないことに忸怩たる思いを抱いています。
物心がついてからの約70年を振り返ってみると、これまでにも世界各国で戦争が行われながら、今ほど自分の問題として戦争の危機を感じたことはなかったような気がします。特に、習近平政権になって以降、中国の覇権主義は益々その度合いを強めている感がし、台湾海峡を巡って、いつ戦いが勃発してもおかしくないような印象を抱いています。恐らく、中国も、直ぐに台湾を武力で統合するような挙に出ることはないとは思いますが、これだけ、大規模かつ頻繁な武力による示威行為を見せつけられると、何かのきっかけで武力衝突が起こり、それが戦争へと発展することが懸念されます。
政権与党である自民党は、結党以来、憲法改正を党是としており、政権が代わる度に、どこまで本気であるかはともかく、憲法改正をその基本方針に掲げています。憲法改正といっても、その対象範囲は極めて広いものの、目指す中心は9条であることは間違いありません。憲法9条については、自衛隊発足以来、約70年にわたって、その合憲性が議論され、その活動の範囲についても、他国から攻撃された場合に、これに反撃する範囲での個別的自衛権は憲法上許されるが、先制攻撃や集団的自衛権の行使は許されないとの解釈に落ち着いたところです。しかしながら、これを突き崩したのが、安倍政権で成立した安保法制といえます。安保法制に至るまでは、官邸と内閣法制局との間で激しいやり取りがあったやに言われていますが、結局、従来の人事慣行を破って、集団的自衛権を容認する元外務官僚を法制局長官に据える異例の人事を行い、いわば力ずくで解釈改憲を強行して法整備を行いました。これによって、集団的自衛権違憲論に一部風穴を開けることとなり、憲法解釈の範囲を逸脱すると厳しい批判を浴びたことは、現在でも鮮明に記憶に残っています。
当時、安倍総理は「現行憲法で、ここまで(安保法制)はできるが、これ以上になると憲法改正が必要になる」と述べていましたが、今後、安保法制以上の対応が必要と判断した場合には「ここまではできる」と解釈を更に変更するのでしょうか。
安保法制当時、自衛隊と憲法の関係も議論となりましたが、その議論は今も続いています。憲法9条2項では「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」と明記されていますので、自衛隊は、ここでいう戦力ではないという解釈に立っているわけですが、世界でもかなり上位にランクされる軍事力を有する自衛隊が戦力ではないというのは、普通の感覚でいえば、到底理解を得られるものではないでしょう。ただ、歴代の内閣は、憲法9条と自衛隊の存在とを両立させるため、他国から攻撃を受けた場合に最小限の反撃を行う個別的自衛権は同条の範囲内として自衛隊の合憲性を認める解釈をしており、文言上は明らかに不自然でありながら、この解釈が国民の間に概ね浸透し、最近では「自衛隊違憲論」を声高に主張する動きは余り見られないように思われます。
自衛隊を憲法上明記することは、それによって、条文と実態との整合性が取れることになるでしょうが、その副作用も十分警戒する必要があります。安倍総理は、在任中、国会等において「自衛隊を憲法に明記しようとすることは、自衛隊は憲法に違反すると考えているからではないか」との問いに対して「自衛隊は合憲である」と明確に答弁しています。そうだとすれば、憲法9条を改正しようが、現状であろうが自衛隊の憲法上の問題は生じないわけですから、何故この改正をするのか、意味不明ということになります。安倍総理としては、どう読んでも、自衛隊合憲の解釈は無理なので、一気に9条を改正して「自衛隊は合憲か違憲か」という長年争われてきた問題に決着をつけたかったものと思われます。
これが、学問の世界、あるいは行政上の実務の問題であれば、法令と実態との乖離を是正することは当然のことですが、憲法、それも9条となると、そう単純にはいきません。憲法改正は、法律等と比較して極めて困難な関門を通らなければならないことはもちろんですが、特に9条に場合、何より配慮すべきことは、外国との関係です。特に、中国との関係は最も慎重に考えるべき問題であり、仮に、日本が憲法9条を改正して、自衛隊を憲法上明確に位置付けたとすれば、「日本は軍事国家に舵を切った」と喧伝し、一層きな臭い状態になることは十分に予想されます。その時「いやー、現在でも憲法上問題がない自衛隊を、誤解が生じないように憲法に明記しただけで、実態は何も変わらないからご心配には及びません」と回答して理解を得られるでしょうか。そう考えると、憲法9条の改正は、中国をはじめとする近隣諸国との緊張を徒に高めるものであって、余りにもリスキーと言わざるをえません。
一般論としては、憲法を含む法令と実態との乖離があり、実態を生かそうとする場合には、まず解釈論としてどこまで許されるかを検討した上、解釈の限界を超える場合に所要の改正をするものですが、特に憲法9条のような、諸外国との関係にも大きな影響をもたらすものの改正に当たっては、それが大きな副作用をもたらすものである以上、慎重の上にも慎重な検討が必要と考えられます。
私は、憲法9条を神聖視するかのような考え方に与するものではありませんが、同条が、軍事力の拡大を抑制し、我が国の平和主義を世界にアピールする役割を果たしてきたことについては高い評価をしています。そうした観点に立てば、上記のような重大なリスクを冒してまで憲法9条を改正することは是非とも避けるべきものと考えます。